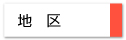冨長蝶如(とみなが ちょうにょ)氏は、静丸(しずまる・本名。号は覚静(かくせい))氏とかぎ氏夫妻の長男として、明治28(1895)年9月1日に生まれた。蝶如は号である。弟が1人おり、息子に覚梁(かくりょう)氏がいる。
昭和63(1988)年12月31日に93歳で亡くなった。
覚梁氏の自宅(長願寺)の書斎に蝶如氏の写真が飾られているが、91歳の頃、大垣文化会館の和室で講演へ行った時のものである。その頃は元気な顔をしていた。同年秋、東京で文部大臣賞の表彰があり、お父様との最後の旅行を兼ねて、覚梁氏も付き添いで行った。
蝶如氏が17、8歳の頃、愛知県弥富町の乾物屋の離れに下宿しながら、服部担風(たんぷう)氏の開いていた漢学の私塾に通い始めた。下宿先から徒歩約10分の担風先生の屋敷まで毎日通い、教えを受けていた。同門に郁達夫(いく たっぷ)氏がおり、その後も長いこと交流を続けるきっかけとなった。
蝶如氏は、後に担風先生と同様に私塾を開き、大正の終わり頃から漢詩を教えていた。また、昭和の初めから大谷大学で教鞭を執っていた。
戦争の始まる少し前、小学生だった覚梁氏は、京都の大学の近くで下宿している父・蝶如氏の所へよく汽車で行き、蝶如氏が講義を終わって帰ってくるのを寂しく待っていた思い出がある。
蝶如氏は漢学に通じていただけでなく、書についても優れていた。例えば、東本願寺の門首から全国の末寺がお講を作る時に、東本願寺門主からお講に対して授ける御文章を書くなど、書記官をしていた。親鸞や蓮如の御遠忌の際に門首が読む願文も蝶如氏が書いていた。願文には東本願寺門主の名前が書いてあり、冨長蝶如氏の名前はないが、書体を見れば冨長蝶如氏の書だということが分かる。その願文の原稿の下書きが長願寺に残っている。
蝶如氏は、新聞にも良く匿名で投稿していた。筆で書いているので誰なのかは、大体分かってしまうが、「養老山麓一老人」と名乗っていた。例えば、田中角栄首相が日中国交正常化で中国へ行った際に持って行った漢詩が新聞に載っていた時は、「(角栄の漢詩は、)詩になっておらず、いっぺんに教養が分かってしまう、誰か力のある人が見るべきだ。」と皮肉めいた文章を投稿し、取り上げられていた。
岐阜県は、鹿児島県と姉妹県である。かつて、岐阜県の人が鹿児島の博物館へ行った時に、九州中の色々な人に見てもらっても一字も判読できない軸物があるので、判読できる人がいないか、と聞かれた。岐阜県の人が蝶如氏の名前を出したところ、夏頃に軸を二幅携えて鹿児島県の方が蝶如氏のもとを訪れた。床の間へ掛けると、ものの1分で蝶如氏は判読してしまった。
大垣共立銀行頭取の土屋斉(つちや ひとし)氏によると、お父様の土屋義雄氏が蝶如氏に漢詩を習っていて、軸物に書かれた漢詩を読んでもらう機会があった。その時に蝶如氏でも一字だけどうしても読めない字があった。蝶如氏の死後、遊びでアルファベットが一字書いてあったことが判明し、誤魔化して読むことをしなかった蝶如氏の人間性が分かったそうである。
蝶如氏が88歳の時に弟子達が建てた蝶如氏の養老瀑泉詩碑が養老公園にある。除幕式は昭和51(1976)年11月3日であった。
公園の中に碑を作る手続きが大変であったが、多くの人の尽力により建立された。
蝶如氏は、愛知県半田の亀崎在住の友人と親しく、半田を訪れたり手紙を出すなどして、亀崎の友人から影響を受けたようである。養老から亀崎までは、今ならなんでもない距離であるが、昔は国鉄で大府で乗り換えて一日がかりで行き一泊しなければならない位の距離であった。子・覚梁氏の自宅長願寺には、蝶如氏の友人たちの手紙が多く残っているが、その中にも亀崎の友人との手紙がある。亀崎は30数台の山車で賑わう祭りが有名で、文化が豊かな所だったようである。
蝶如氏の作った漢詩の会には東京や北海道の人もいた。
蝶如氏は大垣、岐阜、尾張一宮、名古屋の4か所で教えていた。この中で、養老周辺での集まりには、地元の養老の人はあまりおらず、不破郡、大垣、池田町、神戸町、大野町から自転車で来ていた。
夏休みは垂井のお寺や赤坂の金生山(きんしょうざん)の上の明星輪寺(みょうじょうりんじ、虚空蔵さん)を会場にして行なった。漢詩の会は月一回朝9時頃から集まり、午前中は蝶如氏から前もって与えられていた題について漢詩を作って半切に書き一枚ずつ並べ、皆が正座して、蝶如氏がひとつひとつ詠んで添削した。昼は冷麦などで休憩し、2時位から5時位まで蝶如氏の講義があった。
岐阜と一宮に各4、50名の門下生がいた。また、人数は不明であるが名古屋にも門下生がいた。
氷心吟社(ひょうしんぎんしゃ)、湘川吟社(しょうせんぎんしゃ、中国の湘川から付けた)、麋城吟社(びじょうぎんしゃ、麋城=大垣城のこと)という会もあった。一番門下生が多かったのは約34、5名からなる湘川吟社で、集まると寺の御堂がいっぱいになる程だった。湘川吟社は約60年続いた。
大正から昭和40年代の初め位までは漢詩を嗜む人がいたが、蝶如氏の没後は吟社も徐々に衰退してしまった。蝶如氏の主な後継者は、愛知には服部承風(しょうふう)氏、桑名には奥田魚錢(ぎょせん)氏がいるので、その地域ではまだ漢詩を嗜む人が残っている。不破郡に多くいた門下生は、明治生まれが多かったため、今も存命の人は少ない。奥田魚錢氏は蝶如氏の推薦により、雑誌の『大法輪』の漢詩の投稿欄の撰者をしている。
蝶如(ちょうにょ)氏には、垂井にも多くの漢詩の仲間がいた。垂井町表佐(おさ)の阿弥陀寺では、中世から短歌の会があり、いまだに続いている。この寺でも蝶如氏は、漢詩の会を開いている。
郡上市の白山長滝(はくさんながたき)神社の近くにある歴史資料館の建物の床の間に「爛柯堂(らんかどう)」という額があるが、蝶如氏が書いたものである。
蝶如氏の著書『服部担風先生雑記』からは、蝶如氏がどれほど師の服部担風(たんぷう)氏を敬愛していたかが分かる。引き込まれる文章、ざっくばらんな文章からは、蝶如氏自身の人柄が見える。また、毎月蝶如氏が担風先生の月命日に参る姿を覚梁氏が見ていると、とても自分にはできない、と思える。それほど担風先生に影響を受けたのであろう。
覚梁氏は、蝶如氏が『服部担風先生雑記』を書いている姿を見ていたが、漢詩など全て頭に入っていて、殆ど資料なしで書いていた。情景が浮かぶ様に事細かに書かれていている。
蝶如氏の門下生たちの姿を見て、息子の覚梁氏も漢詩を書くようになった。詩を作り、表現し、披露し、勉強している姿は、言葉を学ぶだけではなく、物を見つめ、心が養えるだろうと思ったからである。その姿は有難く、皆いきいきしていた。呑気な事をしていると怒られるかもしれないが、蝶如氏は戦時中も漢詩を書いていた。
蝶如氏の門下生の中には、垂井町表佐出身で、軍隊では大佐だったが復員後に放心状態だったのを両親が心配し、父親が蝶如氏の所で漢詩を学ばせるために連れてきた、という経緯の人もいた。その後漢詩の会に入って、戦後のやりきれない気持ちから変わられて、漢詩集を一冊出された。後にその方は、表佐から名古屋へ移られたそうである。
門下生の中には、名古屋からバスで大垣へ来られていた人も何人かみえた。
江戸時代の美濃では、東濃の岩村に佐藤一斎(さとう いっさい)氏、西濃の大垣に梁川星巖(やながわ せいがん)氏がおり、漢詩が盛んであった。昭和30年代になって、全5巻の『梁川星巖全集』を初代大垣市立垣図書館長と冨長蝶如(ちょうにょ)氏が執筆を行った。1巻編集の途中で図書館長が亡くなり、その後は蝶如氏が全て執筆した。
執筆の際のエピソードとして、真夏で、扇風機もない部屋で、ふんどし一つで執筆していたという。蝶如氏はいつもは筆で書きものをしていたが、この原稿だけは万年筆で書いていた。その時の原稿が現在も残っている。星巖の詩は、中国の諺や、言葉の知識や言葉に含まれる意味が読み込めないと解説できないので、漢詩の中でも難しいと蝶如氏は覚梁(かくりょう)氏に言っていた。
晩年の冨長蝶如(とみなが ちょうにょ)先生に監修して頂いた漢詩を表装したものが小畑公民館の和室に20年位飾ってあり、裏に「冨長蝶如先生監修」と書いてある。
『服部担風先生雑記』は養老町図書館に保存されている。
梁川星厳(寛政元年(1789)~ 安政5年(1858年))は江戸時代後期の漢詩人である。岐阜県安八郡曽根村に生まれた。江戸で玉池吟社を開いて大勢の門弟に漢詩、唐詩を教えた。広瀬淡窓、頼三陽、菅茶山と並ぶ漢詩人である。世人は日本の李白と称した。表示位置は養老瀑泉詩碑を示している。